ごあいさつ
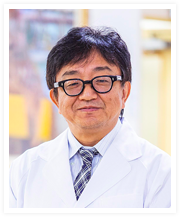
院長
鮫島 隆晃
これからの新しい精神科医療の実現を目指して
さめじま病院は、佐賀県の北部の山あいの川のほとり、自然に恵まれた環境の中にあります。春には梅や桜、菜の花などが鮮やかに咲き、ウグイスなどの野鳥の声に安らぎ、梅雨頃には白鷺も舞い降り、秋には曼珠沙華があぜ道を彩り、紅葉と共に心を和ませてくれます。水も豊かで、失われつつある四季の変化が身近に感じられる癒しの場所です。
さて、戦後の混乱を乗り越え、世界有数の経済大国となったわが国は、欧米のように成熟した社会に近づく一方で、バブル崩壊、リーマンショックを経て、国際競争力の相対的低下と出生率低下による人口減少、そして他国に類をみない超高齢化社会の到来によって岐路に立たされています。
精神科医療に目を向けてみると、「こころの時代」という言葉があちこちで聞かれるようになって久しくなり、社会構造の変化に伴い精神科医療に対するニーズも明らかに変化しています。かつて、明治時代に癲狂院が作られ、呉秀三東大教授が私宅監置の実態を憂い、全国8ヶ所に精神科病院を設置した戦前を経て、戦後の高度経済成長と連動するかのように昭和30年頃から年間1万〜2万床もの精神科病床が増加していた時代がありました。そして、平成の時代も終わり、精神科医療のシステムも変革期を迎えています。
社会構造の変化は疾病構造の変化をもたらし、病と健康の間はますますシームレスになりつつあり、従来型の診療ではニーズをカバーできなくなっています。また、精神科医療は元来他の診療科に先駆けて他職種チームによる医療を行ってきましたが、新しい精神科医療のシステムを考えていく場合、他国の例をみても、まず脱施設化ありきでセーフティーネットの機能しない社会制度下では、病に苦しむ人から健康で文化的な生活をただ奪うことになりかねません。そこには質の高い生活支援、退院支援が適切に行われる必要があり、さらなるチーム力の向上と介護・福祉とのスムーズな連携が求められています。
当院では、こうした時代のニーズの変化を真摯に受け止め、病に苦しむ人、社会から疎外感を受けている人、ストレスに苛まれている人の心に寄り添い、医学・薬学の研鑽と診療看護技術の習得に励み、生活支援に必要な社会制度に精通したケースワークとより良い日常生活に必要なリハビリテーション、適切な栄養管理を通じて、医療専門職としての重責を果たしていきたいと考えています。全職種が、苦しみ悩む人の心に寄り添う医療を目指し、しっかりと地域に根ざした、信頼され、いつでも安心して受けられる医療を実現できるように努力していきます。
最後に、戦争や災害に苦しむ人たちが、一日も早く心安らかに過ごせるよう願って止みません。
さめじま病院 院長
鮫島 隆晃


